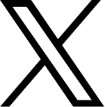お役立ち情報
B工事に相場が無い理由とは?ABC工事の違いと注意点をわかりやすく解説
2025.07.11


オフィスの移転やリニューアルを進める中で、「B工事」という言葉を耳にする機会があるかもしれません。 「A工事やC工事とは何が違うの?」「費用は誰が負担するの?」「どんな点に注意すればいいの?」など、具体的な内容については曖昧な方も多いのではないでしょうか。B工事は、工事区分であり、その理解不足は思わぬトラブルや追加費用につながる可能性もあります。 この記事では、オフィス移転や改装を控えた企業の総務担当者様やプロジェクトご担当者様に向けて、B工事の基本的な知識からスムーズに進めるための注意点やトラブル回避策まで、網羅的に分かりやすく解説します。この記事を読めば、B工事に関する疑問が解消され、安心してプロジェクトを進めるために必要な知識が身につきます。
移転先をこれから探す。まだ決まっていない方へ
コスト重視か?おしゃれを取るか?など悩まれておりましたら、居抜きオフィスはなぜ人気?セットアップオフィスの違いと唯一のメリットを読むことでオフィス探しの一番重要したい部分がわかるかもしれません。
目次
B工事の定義と特徴
B工事とは、テナント(借主)の要望に基づき、テナントが費用を負担して行う工事のうち、ビルオーナー(貸主)が指定する業者によって施工される工事のことを指します。この工事は、主にビルの躯体や共用部分に影響を与える可能性のある設備工事などが対象となります。
B工事の最大の特徴は、費用負担者(テナント)と施工業者の選定者(ビルオーナー)が異なる点にあります。これにより、ビル全体の資産価値や安全性を維持しつつ、テナントのニーズにも応えるというバランスを取っています。
A工事・B工事・C工事との違いと責任範囲
オフィスの工事区分には、B工事の他にA工事とC工事があります。これらの違いを理解することは、費用の負担や責任の所在を明確にし、トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。それぞれの特徴を比較しながら見ていきましょう。
以下に、A工事・B工事・C工事の主な違いをまとめました。
| 項目 | A工事 | B工事 | C工事 |
| 工事内容例 | ビル躯体、共用設備の大規模修繕、耐震補強など | 空調、防災、給排水設備の新設・変更(ビル指定業者施工) | テナント専有部内の内装、間仕切り設置、オフィス家具設置。ど |
| 発注者 | ビルオーナー | テナント(ビルオーナー承認の上) | テナント |
| 施工業者 | ビルオーナーが指定 | ビルオーナーが指定 | テナントが選定 |
| 費用負担者 | ビルオーナー | テナント | テナント |
| 主な目的 | ビルの維持管理、資産価値向上 | テナントの要望による設備改修(ビル全体の機能・安全性を考慮) | テナントの利便性向上、デザイン変更 |
この表を参考に、自社が行いたい工事がどの区分に該当するのかを事前に確認することが重要です。
A工事の範囲と費用負担者
A工事は、ビル本体の構造に関わる工事や、ビル全体の共用部分の修繕、改修工事を指します。建物の外壁、屋上防水、エレベーター、共用廊下、共用トイレなどが含まれます。
A工事の費用はビルオーナーが負担し、施工業者もビルオーナーが選定・発注します。 テナントの要望で実施されるものではなく、ビル全体の維持管理や資産価値向上のために行われるのが一般的です。
B工事の範囲と費用負担者
B工事はテナントの要望により、ビルオーナーが指定する業者が施工し、費用はテナントが負担する工事です。主に、テナントの専有区画内であっても、ビル全体の機能や安全性に影響を与える設備(空調、防災、給排水など)の変更や増設が対象となります。
またビルのグレードが上がると、床壁(間仕切り工事など)もビル全体の機能や安全性のために、B工事になることがあります。正確な区分はオフィスの契約時に確認するようにしましょう。B工事の費用はテナントが負担し、施工業者はビルオーナーが指定します。 この点がA工事やC工事との大きな違いです。
C工事の範囲と費用負担者
C工事は、テナントの専有区画内で行われる内装工事や設備工事のうち、ビル本体や共用部分に影響を与えないものを指します。例えば、間仕切り壁の設置、壁紙や床材の変更、照明器具の取り付け、オフィス家具の設置などが該当します。
C工事の費用はテナントが負担し、施工業者もテナントが自由に選定・発注できます。 ただし、工事内容によってはビルオーナーの承認が必要となる場合もあります。
B工事の具体的な工事範囲と事例
B工事には、テナント専有部の利便性向上を目的としながらも、ビル全体の構造や設備、他のテナントに影響を及ぼす可能性がある工事が含まれます。
代表的な例としてを以下のようなものがあります。ただし、ビルごとの規定や契約内容によってB工事の範囲は異なる場合があるため、必ず契約書やビル管理会社に確認することが大切です。
空調設備の新設・移設・増設
テナントのレイアウト変更や人員増に伴い、個別の空調機を新設したり、既存の空調機の位置を変更したりする工事です。ビル全体の空調システムと連動している場合が多く、ビル指定の専門業者が施工します。
防災設備(スプリンクラー・感知器など)の変更
間仕切り壁の新設やレイアウト変更によって、消防法に基づきスプリンクラーヘッドや煙感知器などの移設・増設が必要になる場合があります。これらの防災設備はビル全体の安全に関わってます。
給排水設備・衛生設備の変更
ミニキッチンや給湯室などをテナント専有部内に新設・移設する場合、ビル全体のインフラに関わるため、ビル共用の給排水管に接続する工事が必要になります。
防水工事
テナント専有部内であっても、水回り設備の新設などに伴い、特に下階への漏水リスクがあるような床面などに防水処理を施す必要がある場合があります。
分電盤工事や幹線工事
テナントが使用する電力量が増加し、既存の分電盤では容量が不足する場合など、分電盤の交換や増設、ビル共用部からの幹線引き込み工事などがB工事として扱われることがあります。
B工事の見積もりのポイント
B工事の費用はテナント負担となるため、コスト管理は非常に重要です。費用が高くなりやすい理由を理解し、見積もり取得時の注意点を押さえておきましょう。
B工事の費用はなぜテナント負担なのか?
「会議室を増やすために空調を増設したい」といったようなテナントのニーズに応えるための工事がB工事に該当し、テナントの事業活動や利便性向上のために行われるため、その費用はテナントが負担するというのが基本的な考え方です。
B工事の費用が高くなりやすい理由
主な理由として、ビル指定業者の利用、中間マージンの発生、ビルごとの独自ルールが挙げられます。ビルオーナーが指定する業者しか利用できないため競争原理が働きにくく、ビル管理会社などが間に入ることで中間マージンが上乗せされることがあります。
また、ビルごとに安全基準が厳格に定められている場合があり、コストアップにつながることもあります。
見積もり取得時の確認事項
B工事の見積もりを取得する際には、工事範囲の明確化、詳細な内訳、諸経費の内容を確認することが重要です。どこからどこまでがB工事の範囲かを図面などで明確にし、「一式」ではなく各工事項目の単価や数量が明記されているか、さらに現場管理費などの内訳や算出根拠を確認しましょう。
費用を適切に抑えるための交渉術
B工事では業者選定の自由がないため価格交渉は難しいですが、工事の必要性の再検討、仕様・グレードの見直し、ビルオーナー・管理会社との協議といった点を意識することで、費用を適切に抑えられる可能性があります。本当に必要な工事か優先順位を見直したり、オーバースペックになっていないか検討したりすることが有効です。
また、費用の妥当性について、ビルオーナーや管理会社に相談することも検討するとよいでしょう。。
【図解】オフィス移転にかかる費用は?概算から詳細な内訳まで紹介! | 居抜き物件ならつながるオフィス
B工事のメリットとデメリット
B工事には、テナント側・ビルオーナー側のそれぞれにメリットとデメリットが存在し、これらを理解することで、より円滑なコミュニケーションと意思決定が可能になります。
テナント側のメリット・デメリット
テナント側のメリットとしては、ビル全体の安全性・機能性の維持に加え、専門業者による高品質な施工が挙げられます。ビル指定の専門業者が工事を担当するため、設備に関する知識や経験が豊富であり、施工の品質が安定しています。また、ビルの構造や設備を熟知しているので、工事の進行もスムーズに行われる傾向があります。
一方で、テナント側のデメリットとしては、業者選定の自由がないこと、費用が高くなりがちなこと、交渉の難しさが挙げられます。相見積もりによる価格競争が働きにくく、前述の理由や中間マージンなどにより費用が高くなる傾向があり、価格や工事内容についての交渉が難しい場合があります。
ビルオーナー側のメリット・デメリット
ビルオーナー側のメリットには、ビル全体の資産価値維持、工事品質の担保、トラブルリスクの低減が挙げられます。ビル全体の統一された品質基準で工事が行われるため資産価値を維持しやすく、信頼できる指定業者が施工するため工事の品質を管理しやすくなり、不適切な工事による事故・故障のリスクを回避できます。
他方で、ビルオーナー側のデメリットとしては、テナントとの調整業務の発生や指定業者の管理責任が挙げられます。テナントの要望とビル側の基準をすり合わせるための調整業務が必要になり、指定業者の選定や指導など、一定の管理責任が生じます。
B工事をスムーズに進めるための注意点とトラブル回避策
B工事は関係者が多く、調整事項も複雑なため、注意点を押さえて慎重に進める必要があります。ここでは、よくあるトラブルとその回避策について解説します。
契約前に工事区分をしっかり確認する
最も重要なのは、賃貸借契約を締結する前に、A工事・B工事・C工事の区分がどのように定められているかを確認することです。契約書本体だけでなく、添付されている「工事区分表」などを細部まで読み込みましょう。不明な点は必ずビルオーナーや管理会社に質問し、書面で回答を得ておくことが賢明です。
ビルオーナー・管理会社との密な連携
B工事の計画段階から完了まで、ビルオーナーや管理会社とのコミュニケーションを密に取ることが不可欠です。
- 工事計画の早期共有: テナントの要望や計画をできるだけ早い段階で伝え、協議を開始するようにしましょう。
- 定期的な打ち合わせ: 進捗状況や問題点を共有するため、定期的に打ち合わせの場を設けましょう。
- 議事録の作成: 打ち合わせ内容や決定事項は、必ず議事録として書面に残し、双方で確認するようにします。
工事のスケジュール管理と工期遅延リスク
B工事はビル指定業者が施工するため、その業者のスケジュールによって工期が左右されることがあります。移転スケジュールに影響が出ないよう、できるだけ早めに工事計画を立て、業者との日程調整を進めることが重要です。また、万が一の遅延に備えて、スケジュールにはある程度のバッファを持たせておきましょう。
原状回復義務との関連性を把握する
B工事で実施した内容は、原則としてテナントが退去する際に原状回復の対象となることが多いです。どこまでが原状回復の範囲に含まれるのか、工事着手前にビルオーナーと明確に取り決めておく必要があります。
B工事の一般的な流れと進め方
B工事を実際に進める際の一般的な流れを理解しておきましょう。これにより、各段階で何をすべきか、誰と連携すべきかが明確になります。
オフィス移転のスケジュールの目安は?ポイントやおすすめの時期も紹介!! | 居抜き物件ならつながるオフィス
手順1:工事計画とビルオーナーへの相談
テナント側でどのような工事を行いたいのか、具体的な要望をまとめます。その上で、ビルオーナーまたは管理会社に工事計画の概要を伝え、B工事に該当するかどうか、進め方について相談します。
手順2:ビル指定業者による現地調査と見積もり取得
ビルオーナーまたは管理会社を通じて、指定されたB工事業者に連絡を取り、業者は現地調査を行い、テナントの要望やビルの状況を確認した上で、工事の見積書を作成します。
手順3:見積内容の精査と発注
提出された見積書の内容をテナント側で精査し、費用、工事範囲、工期などが妥当であるかを確認し、必要であれば業者やビルオーナーと調整を行います。見積内容に合意できたら、ビルオーナーの承認を得て、正式に工事を発注します。
手順4:施工と進捗管理
契約に基づき、指定業者が工事を開始します。テナントは、工事の進捗状況を定期的に確認し、計画通りに進んでいるかなどをチェックします。工事中に変更点や問題が発生した場合は、速やかに関係者で協議し対応します。
手順5:完了確認と引き渡し
工事が完了したら、テナント、ビルオーナー、施工業者の三者で図面や仕様書通りに仕上がっているかどうか最終確認(竣工検査)を行います。問題がなければ、工事完了報告書などを受け取り、引き渡しとなります。
【原則】B工事に相場がない理由
B工事はオーナー指定の工事の施工会社を指定できる関係上、材料の品質や施工レベルによって同じ工事であっても金額が施工会社によって大きく変わってしまう性質があります。
ただ、この記事を読んでいただいている方であれば、「施工箇所があらかた決まっていれば相場って出せるのでは?」って思うはず。もちろん、すべてのB工事に該当する施工場所が一律であればそうでしょう。
しかし、B工事の相場が出せないのには理由があります。それはビルのグレード・ビルを保有する不動産会社(オーナー)によってB工事に該当する箇所が変わってしまうことです。
例えば、弊社の事例でも床材の工事の際に、A社が保有するビルではC工事(テナント指定の業者選定)が出来るのに対して、B社が保有するビルでは床工事がB工事に該当してケースが往々に存在します。
工事個所(施工内容)がビルによって、C工事になったりB工事になるので、相場を出すのはとても難しいのです。よって、当社でおすすめしておりますのは、契約前にB工事の範囲を確認しておくこと。
施工内容から逆算して内装費を把握することが可能になるだけでなく、契約時の交渉等にも失敗する確率を大きく下げることが可能になるのです。
B工事は高い。経費を安くしたい企業はセットアップオフィスへ
B工事はどうしてもオーナー指定業者による施工になるので。一般的なC工事の相場に比べて3割~5割は高くなってしまいます。
内装費にお金を掛けられない従業員数50~150名の企業様には、内装費0×工数0のセットアップオフィスをお勧めしております。
個性を出したい企業様向けのデザイン性が高いスケルトン天井のオフィスをはじめ、金融系などのおしゃれよりも高級感を重視される企業様にも使いやすい内装オフィスです。
中には敷金0から移転できる物件もありますので、移転の選択肢として一度ご確認ください。
【社員数50名以上向け】100坪以上の内装付きオフィス一覧はこちら
まとめ
B工事は、オフィス移転やリニューアルにおいて避けて通れない重要なプロセスです。その特徴や注意点を正しく理解し、関係者と良好な連携を取ることで、理想のオフィス環境を実現しましょう。
オフィスのレイアウト工事のABC工事はわかったが、そもそもどんなレイアウトがある?と思われた方は、オフィスレイアウトは重要!基本の7パターンと成功させるコツを解説もご覧ください。
CONTACT US CONTACT US
居抜きオフィス物件の
入居・募集なら
つながるオフィスへお任せください


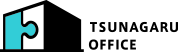
 居抜き物件を探す
居抜き物件を探す