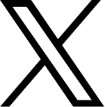お役立ち情報
テナントの原状回復とは?費用の相場と工事の範囲を分かりやすく解説
2025.08.20


オフィスの移転に伴い、避けては通れないのが「原状回復」です。しかし、「どこまで元に戻せばいいのか」「費用はどれくらいかかるのか」など、多くの疑問や不安がつきまとうのではないでしょうか。特に事業用のテナント物件における原状回復は、普段私たちが接する居住用の賃貸住宅とはルールが大きく異なります。 知識がないまま進めてしまうと、想定外の高額な費用を請求されたり、貸主であるオーナーとトラブルに発展したりするケースも少なくありません。 本記事では、テナントの原状回復について、基本的な定義から費用の相場、工事の範囲、そしてトラブルを未然に防ぐための具体的なポイントまで、分かりやすく解説していきます。
目次
テナントの原状回復とは?
テナントの退去を考える上で、まず最初に理解しておくべきなのが「原状回復」の基本的な考え方です。特に、一般的なアパートやマンションなどの「居住用物件」のルールとは異なる点が多いため、その違いを正確に把握することが重要になります。
そもそも原状回復とは何を指すのか
原状回復とは、賃貸物件の契約が終了し退去する際に、借主が物件を入居した時の状態に戻す義務のことを指します。これは、借主が設置したものを取り除いたり、事業の運営によって生じた汚れや傷などを修復したりする工事を意味します。
ただし、これは「新品の状態に戻す」ことではありません。法律上、そして国土交通省が示すガイドラインでは、この定義がトラブルを避けるための重要な基準となります。
テナントに求められる原状回復のレベル
事業用であるテナント物件では、居住用物件に比べて厳格な原状回復が求められるのが一般的です。オフィスや店舗では、運用に合わせて会議室の追加や造作家具の設置などの内装の変更や特別な設備の設置など、事業内容に応じたカスタマイズがされていることが多いためです。
契約内容にもよりますが、「入居時の状態に完全に戻す」ことを求められるケースが多く、借主の負担範囲が広くなる傾向にあります。
居住用物件の原状回復との明確な違い
居住用物件とテナント物件の原状回復における最大の違いは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の適用範囲にあります。このガイドラインは、主に居住用物件を想定しており、テナント物件には法的な拘束力がありません。
引用文献:住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について – 国土交通省
| 比較項目 | テナント物件(事業用) | 居住用物件 |
| 基本方針 | 賃貸借契約書の内容が絶対的な基準となる。特約が重視される。 | 国土交通省のガイドラインが基準となることが多い。 |
| 通常損耗・経年劣化の扱い | 契約書の条文中に、床壁天井の張替えをする旨が記載され、借主が負担するケースが多い。 | 原則として貸主(オーナー)が負担する。 |
| 工事のタイミング | 契約期間内に工事を完了させ、明け渡す必要がある。 | 退去後に工事が行われるのが一般的。 |
| 費用負担 | 原則として借主が全額負担することが多い。 | 借主の故意・過失部分のみ負担し、敷金から相殺されることが多い。 |
このように、テナントの原状回復は契約書の内容がすべてと言っても過言ではありません。そのため、契約内容を正しく理解することが、適正な原状回復を行うための第一歩となります。
テナントの原状回復義務の範囲はどこまで?
「一体、どこからどこまでを元に戻せば良いのか?」これは、原状回復において最も重要なポイントです。工事の範囲が1つ違うだけで、費用は大きく変動します。ここでは、原状回復義務の範囲がどのように決まるのかを詳しく見ていきましょう。
原則は賃貸借契約書の内容に従う
テナントの原状回復範囲を決定づける最も重要な書類は、入居時に交わした「賃貸策契約書・関連書類」です。契約書に「乙(借主)の負担において、本物件を契約締結時の状態に復して甲(貸主)に明け渡す」といった条文があれば、それに従う義務が生じます。特に、契約書の条文中、通常損耗の扱いなど、より具体的なルールが記載されていることが多いので、必ず細部まで確認しなくてはなりません。
国土交通省のガイドラインは適用されるのか
前述の通り、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、あくまで居住用物件を対象として作成されたものです。そのため、オフィスや店舗といった事業用テナントには、このガイドラインが直接適用されるわけではありません。
しかし、裁判などではこのガイドラインの考え方が参考にされることもあります。契約書の内容に不明確な点がある場合の交渉材料にはなり得ますが、基本的には契約書の効力が優先されると理解しておくべきです。
通常損耗と経年劣化の扱いはどうなるのか
通常損耗とは、家具の設置による床のへこみや、ポスターを貼っていなかった壁紙が日焼けで変色するといった、普通に使っていても発生する損耗のことです。経年劣化は、時間の経過とともに品質が低下することを指します。
居住用物件では、これらは貸主負担で修繕するのが原則です。しかし、テナント物件の場合は、「通常損耗や経年劣化を含めて、借主の負担で原状回復を行う」という契約が結ばれているケースが非常に多いのが実情です。 この特約の有無で費用負担が大きく変わるため、契約書の確認が不可欠です。
居抜き物件の注意点
居抜き物件: 居抜きで入居した場合でも、原状回復義務は前テナントより引き継ぐため、契約書に「退去時はスケルトンで」と記載されていれば、解体費用はすべて自社の負担となります。退去時の条件を勘違いしてトラブルになるケースが多いため、入居時の契約内容は必ず確認しましょう。
テナントの原状回復工事にかかる費用の相場
原状回復の範囲と並んで気になるのが、工事にかかる費用です。相場を把握しておくことで、業者から提示された見積もりが適正かどうかを判断する基準になります。
費用の内訳と基本的な算出方法
原状回復工事の費用は、主に以下の項目で構成されています。
- 仮設工事費: 養生や工事用の間仕切り設置など。
- 解体工事費: 内装、間仕切り、造作物の撤去。
- 内装仕上げ費: 天井、壁、床の再塗装や張り替え。
- 設備工事費: 照明、空調、防災、給排水設備の修繕・撤去。
- その他諸経費: 産廃処理費、現場管理費など。
費用は「坪単価 × 広さ」で概算されることが多いですが、物件の状態や工事内容によって大きく変わるので、見積を依頼し、確認するようにしましょう。。
【坪数別】オフィス・店舗の費用相場
物件の規模ごとの費用相場は以下の通りですが、あくまで目安として考えてください。
| テナント規模 | 目安坪数 | 原状回復工事の目安坪単価 |
| 小規模テナント | 50坪未満 | 3万円~7万円 |
| 中規模テナント | 50~100坪 | 6万円~10万円 |
| 大規模テナント | 100坪~300坪 | 8万円~15万円 |
例えば、50坪の中規模オフィスであれば、300万円~500万円程度がひとつの目安となります。
費用が高額になりやすいケースとは
以下のようなケースでは、相場よりも費用が高額になる傾向があります。
- スケルトン返しが条件の場合: 解体範囲が広いため、費用は高くなります。
- 飲食店などの重飲食店舗: 厨房の防水工事や排気ダクトの清掃・撤去など、特殊な工事が必要になるためです。
- B工事の割合が多い場合: 貸主が指定する業者(B工事)の見積もりは、借主が自由に選定する業者(C工事)に比べて高額になることが一般的です。
- アスベスト(石綿)の除去が必要な場合: アスベスト調査記録がないビルの場合は、解体時にアスベストの調査や除去が必要となり、追加で高額な費用が発生することがあります
工事の種類についてはB工事とは?費用相場からA・C工事との違い、注意点まで徹底解説を読むことで工事範囲がわかります。自社指定の工事会社でできる箇所があった場合、退去費用の交渉の余地が生まれるかもしれません。
テナントの原状回復工事を進める手順
退去が決まってから慌てないように、原状回復工事の全体的な流れを把握しておきましょう。一般的に、退去の6ヶ月前には準備を始めるのが理想です。
賃貸借契約書の内容を再確認する
すべての基本となるのが賃貸借契約書です。まずは契約書と関連書類(工事区分表など)を隅々まで読み返し、「原状回復の範囲」「貸主と借主の費用負担区分」「解約予告期間」「指定業者の有無」などを正確に把握します。
貸主(オーナー)と協議し工事範囲を確定する
契約書の内容だけでは判断が難しい部分や、不明確な点については、必ず貸主(ビルオーナーや管理会社)と協議の場を設けます。双方の認識をすり合わせ、どこまで工事を行う必要があるのかを具体的に確定させます。この協議内容を議事録として書面に残しておくことが、後のトラブル防止につながります。
工事業者を選定し見積もりを依頼する
工事範囲が確定したら、工事業者に見積もりを依頼します。貸主から業者の指定がない場合(C工事)は、複数の業者から相見積もりを取るのが基本です。見積書は金額だけでなく、工事内容の詳細、工期、保証の有無などを比較検討し、信頼できる業者を選びましょう。
原状回復工事の実施と引き渡し
選定した業者と契約を結び、工事を開始します。工事は賃貸借契約の期間内に完了させる必要があります。 工事完了後、貸主の立ち会いのもとで最終確認を行い、問題がなければ物件を引き渡して完了となります。敷金や保証金が返還される場合は、この後に精算されるのが一般的です。
原状回復費用を抑えてトラブルを回避する4つのポイント
最後に、多額の費用がかかる原状回復を少しでも安く、そして円満に進めるための実践的なポイントを4つご紹介します。
入居時の状態を写真で記録しておく
退去時に「これは元からあった傷だ」と主張しても、証拠がなければ認められない場合があります。トラブルを避けるために、入居時に気になるところがあったら、オーナーに報告したほうが良い場合もあるので、入居時に物件の隅々まで写真を撮っておきましょう。日付の入る設定で撮影し、データとして保管しておけば、貸主との協議の際に有力な証拠となります。
複数の業者から相見積もりを取得する
貸主から業者の指定がない限り、必ず2〜3社から相見積もりを取り、価格と内容を比較検討しましょう。これにより、適正な市場価格を把握でき、不当に高い費用を請求されるリスクを減らせます。専門用語が多くて分かりにくい場合は、業者に説明を求めることが大切です。
貸主指定のB工事は内容を精査する
B工事(貸主が指定した業者で行う工事)は、ビルの構造に関わる重要な工事が含まれるため避けられませんが、費用が高額になりがちです。提示された見積もりに対して、内訳の明確化を求め、不要な工事項目が含まれていないか、単価は適正かを厳しくチェックしましょう。専門家の助けを借りて査定を依頼するのも有効な手段です。
居抜き退去を検討する
原状回復費用を大幅に削減できる可能性があるのが「居抜き退去」です。これは、自社の内装や設備を次のテナントに引き継いでもらう方法です。
貸主の承諾が必要ですが、原状回復無しで居抜き退去するルールに則って居抜き退去に成功すれば、原状回復工事が不要になり、数百万円単位のコストを削減できる可能性があります。
まとめ
テナントの原状回復は、事業用物件ならではのルールが多く、複雑に感じられるかもしれません。しかし、最も重要なのは「賃貸借契約書の内容を正しく理解し、貸主と事前にしっかりと協議すること」です。本記事で解説したポイントを押さえ、計画的に準備を進めることで、費用を適正に抑え、トラブルのないスムーズな退去を実現してください。
退去通知を貸主(ビルオーナー)行ったけど、移転先をこれから探す。まだ決まっていない方へ
コスト重視か?おしゃれを取るか?など悩まれておりましたら、居抜きオフィスはなぜ人気?セットアップオフィスの違いと唯一のメリットを読むことでオフィス探しの一番重要したい部分がわかるかもしれません。
CONTACT US CONTACT US
居抜きオフィス物件の
入居・募集なら
つながるオフィスへお任せください


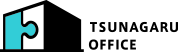
 居抜き物件を探す
居抜き物件を探す