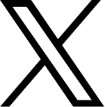お役立ち情報
BCP対策に強いオフィスとは?具体的な選び方と環境づくりのポイントを解説!
2025.08.15


自然災害や感染症のパンデミックなど、企業活動を脅かす不測の事態はいつ起こるか分かりません。そのような緊急事態においても事業を継続し、従業員と会社を守るための計画が「BCP(事業継続計画)」です。本記事では、企業の根幹であるオフィスのBCP対策に焦点を当て、その重要性から具体的なオフィスの選び方、環境構築、そしてBCP策定の流れまで、担当者が知っておくべきポイントを網羅的に解説します。
BCP(事業継続計画)とは?
BCP(Business Continuity Plan)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃といった緊急事態に遭遇した際に、資産の損害を最小限に抑えつつ、中核となる事業を継続、あるいは早期に復旧させるための方針や手順などをまとめた計画です。 変化が激しく、予測困難な現代において、企業の存続に不可欠なリスク管理の一つとして、その重要性はますます高まっています。
なぜ今オフィスにBCP対策が必要なのか
東日本大震災や近年のパンデミックを経て、多くの企業が事業停止の危機に直面しました。 オフィスは事業活動の中心地であり、従業員が集まる場所です。このオフィスが機能不全に陥ると、事業の継続は極めて困難になります。BCP対策を講じることは、従業員の安全を守るだけでなく、取引先や顧客からの信頼を維持し、企業価値を守る上で極めて重要な取り組みです。災害発生後、迅速に事業を再開できる体制は、企業の競争力にも直結します。
防災対策との違い
防災対策とBCP対策は混同されがちですが、その目的と範囲には明確な違いがあります
| 観点 | 防災対策 | BCP対策 |
|---|---|---|
| 目的 | 人命や物的資産を守ること(被害の軽減) | 重要業務を継続・早期復旧させること(事業の継続) |
| 対象 | 主に地震や火災などの自然災害 | 自然災害、感染症、テロ、情報漏洩、サプライチェーンの寸断などの多様なリスク |
| 時間軸 | 災害発生時の初動対応が中心 | 平常時の準備から緊急時の対応、復旧まで長期的な対応が中心 |
防災対策はBCPの一部であり、BCPは防災対策を包含した、より広範で経営的な視点に立った計画であると言えます。
BCP対策を意識したオフィスビルの選び方
効果的なBCPの第一歩は、災害に強いオフィスビルを選ぶことから始まります。オフィスの移転や新設を検討する際は、以下のポイントを必ず確認しましょう。
ハザードマップで立地のリスクを確認する
まず、自治体が公表しているハザードマップを確認し、オフィス所在地の災害リスクを把握することが不可欠です。 地震による揺れやすさ、津波や洪水による浸水の可能性、土砂災害の危険性などを事前に確認し、リスクの低いエリアを選ぶことが基本です。また、避難経路や周辺の避難場所についても事前に確認しておきましょう。
建物の耐震・制震・免震性能を見極める
日本の建築基準法では耐震基準が定められていますが、特に1981年6月1日以降の「新耐震基準」を満たしているかは最低限の確認項目です。 さらに、建物の構造にも注目しましょう。
| 構造 | 特徴 |
|---|---|
| 耐震構造 | 建物の柱や梁を強化し、地震の揺れに「耐える」構造。 |
| 制震構造 | ダンパーなどの装置で地震の揺れを「吸収」し、建物の変形を抑える構造。 |
| 免震構造 | 建物と基礎の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に「伝えない」構造。 |
より高い安全性を求めるのであれば、制震構造や免震構造を採用したビルが望ましいです。
非常用電源や電力供給方式を調べる
大規模災害時には、停電によって事業活動が完全に停止するリスクがあります。そのため、非常用発電機や蓄電池の有無、そしてその燃料がどれくらいの時間(例えば72時間)供給可能かを確認することが重要です。 また、電力の受電方式が複数系統から供給される「ループ受電」など、信頼性の高い方式であるかも、オフィスを選定する際のチェックポイントとなります。
給排水設備と備蓄倉庫の有無を確認する
災害時には断水も想定されます。トイレ機能の維持は衛生環境の確保に不可欠であり、雨水や井戸水を利用できるか、貯水槽が設置されているかなどを確認しましょう。 また、東京都の「帰宅困難者対策条例」のように、事業者が従業員のために3日分の水や食料、簡易トイレなどを備蓄することが求められています。 ビル側で備蓄倉庫が用意されているかもオフィスを選定する際の重要な基準です。
オフィス入居後に実施できるBCP対策
BCPに強いビルを選ぶだけでなく、オフィス内での対策も同様に重要です。現在入居中のオフィスでも、以下の対策を実施することでBCPを大幅に強化できます。
家具やIT機器の転倒・落下防止対策を行う
地震の揺れによるオフィス家具やコピー機、サーバーなどの転倒・落下は、従業員の負傷や避難経路の妨げに直結します。 L字金具での壁への固定や、床への固定、突っ張り棒の設置など、オフィス家具をしっかりと固定しましょう。特にサーバーラックなどの重要機器は、データの損失を防ぐためにも確実な対策が必要です。
安全な避難経路を確保し維持する
避難経路を示す通路に、荷物やキャビネットなどを置かないことを徹底しましょう。 定期的にオフィス内を点検し、避難の妨げになるものがないか確認する習慣が大切です。また、防火扉や消火器の前に物を置かないことも基本です。
データのバックアップと情報共有手段を確立する
企業の重要データは、社内サーバーだけでなく、物理的に離れたデータセンターやクラウド上にもバックアップを取ることで、データ消失のリスクを大幅に低減できます。 また、災害発生時の安否確認や緊急連絡の方法も複数用意しておくことも重要です。安否確認システムやビジネスチャットツールなどを活用し、定期的な訓練を行うことで有事の際に迅速かつ確実な対応が可能になります。
テレワーク体制を整備しリスクを分散する
テレワーク(在宅勤務やサテライトオフィス勤務)の体制を整えることは、非常に有効なBCP対策です。 災害やパンデミックで従業員が出社できなくなった場合でも、自宅や別拠点などから業務を継続でき、事業の完全停止を回避できます。拠点が分散されることで、感染症のリスク分散にも繋がります。
| 対策項目 | 具体的なアクション |
|---|---|
| ITインフラ | VPN接続の整備、クラウドツールの導入、ノートPCの貸与 |
| セキュリティ | デバイス管理、アクセス制限、セキュリティ教育の実施 |
| 労務管理 | 勤怠管理システム、コミュニケーションルール整備 |
| 業務プロセス | ペーパーレス化の推進、オンライン会議の定着 |
サテライトオフィスの概要やメリット、導入事例ついては合わせて以下の記事をご確認ください。
サテライトオフィスとは?メリット・デメリットや事例・導入手順まで解説!
感染症対策を徹底する
新型コロナウイルスの経験から、感染症対策もBCPの重要な柱となりました。 ソーシャルディスタンスを確保できる座席レイアウトの工夫、換気の徹底、消毒液の設置、非接触型システムの導入(自動ドア、顔認証など)が有効です。これらの対策は、新たな感染症の発生に備える上でも役立ちます。
BCP策定の具体的な5つの流れ
BCPは一度策定して終わりではなく、継続的に見直し・改善していくことが重要です。。以下の5ステップに沿って策定をすすめましょう。。
基本方針を決定する
まず、「何のためにBCPに取り組むのか」という基本方針を明確にします。「従業員の命を守る」「顧客への供給責任を果たす」など、企業の理念に沿った目的を設定することで、全社的な取り組みの軸が定まります。
優先する中核事業を特定する
緊急時には、限られたリソース(人、物、金、情報)で事業を継続しなければなりません。全ての事業を同時に復旧させるのは困難なため、「停止した場合に最も経営へのインパクトが大きい事業」や「顧客や社会への影響が大きい事業」を中核事業として特定し、優先順位を明確につけることが重要です。
具体的な計画を策定する
特定した中核事業を継続・復旧させるための具体的な計画を立てます。目標復旧時間(RTO)を設定し、その時間内に事業を再開するために必要な人員、代替拠点、設備、資金、情報システムなどを洗い出し、具体的な手順を文書化します。
全社で共有し、教育・訓練を実施する
策定したBCPは、経営層から全従業員まで、社内全体で共有し、実践できる状態にしておく必要があります。定期的な研修や、災害を想定した訓練(安否確認訓練、避難訓練など)を実施することで、BCPを「知っている」から「できる」レベルへと引き上げ、いざという時に実効性のあるものにします。
定期的に見直しと改善を行う
事業内容の変化、組織変更、新たなリスクの出現などに合わせて、BCPは定期的に見直す必要があります。訓練で明らかになった課題や、社会情勢の変化などを踏まえて計画を更新し、常に実効性の高い状態を維持することが重要です。
まとめ
オフィスのBCP対策は、単なるコストではなく、企業の未来を守るための重要な投資です。本記事で解説したオフィスの選び方や環境づくりのポイント、策定ステップを参考に、自社の状況に合わせた実効性の高いBCPを構築してください。不測の事態に備えることが、企業の持続的な成長と発展に繋がります。
CONTACT US CONTACT US
居抜きオフィス物件の
入居・募集なら
つながるオフィスへお任せください


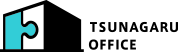
 居抜き物件を探す
居抜き物件を探す